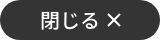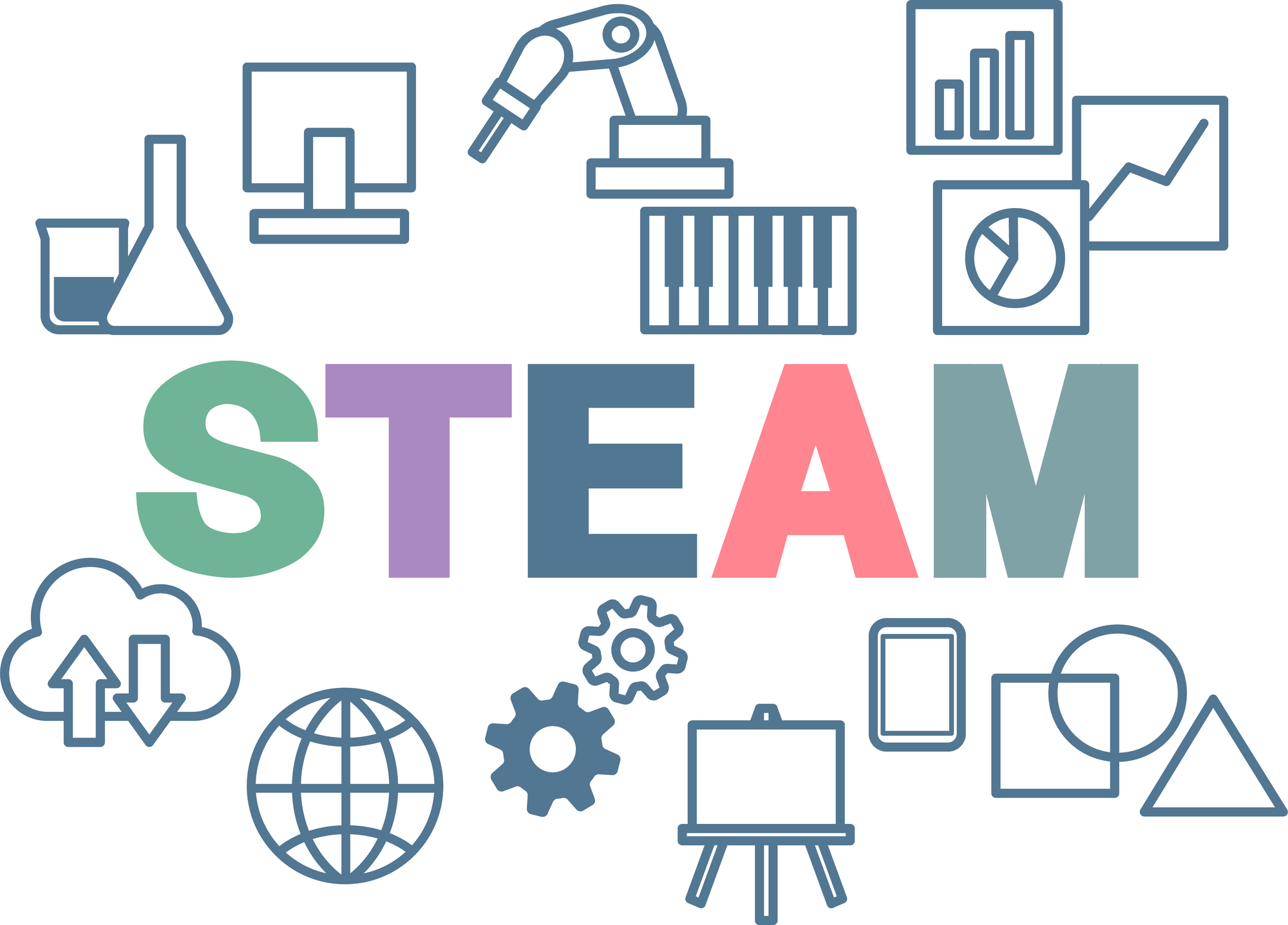ビットコインは今後どうなる?価格推移や利活用の動向を踏まえて徹底分析!

近年、「ビットコイン」という単語を見聞きする機会が増えています。「ビットコインは、今後どのように使われ、価格はどのように推移するのだろうか」と気になっているかもしれません。
そこで、本記事では、ビットコインの特長や活用事例、これまでの歴史・価格推移を紹介した上で、今後どうなるのかを考察します。投資を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
ビットコイン(Bitcoin)とは?
ビットコイン(Bitcoin、BTC)とは、「Satoshi Nakamoto」と称する匿名の人物(またはグループ)によって開発された暗号資産で、2009年1月に最初のブロックが生成されました。ここでは、ビットコインの特長を3つ紹介します。
発行者・中央管理者が存在しない
日本円・ユーロ・米ドルなどの法定通貨には、それぞれ日本銀行・ECB・FRBといった発行者・中央管理者が存在します。
しかし、ビットコインでは、ブロックチェーン技術(取引データをまとめた「ブロック」をチェーンのようにつなげ、ネットワーク上で分散管理する仕組み)が用いられており、発行者・中央管理者が存在しません。多数のネットワーク参加者が相互に監視しながら分散管理しており、記録の改ざんが防止されています。
コンセンサスアルゴリズムとして「Proof of Work」が採用されている
ビットコインでは、コンセンサスアルゴリズム(トランザクションを承認するルール)として「Proof of Work(PoW)」が採用されています。
PoWとは、ネットワーク参加者がコンピューターで複雑な計算を実施することにより、取引の内容を検証・承認し、新規ブロックを生成する仕組みです。もっとも早く計算した者に対して、報酬としてビットコインが付与されます。なお、承認作業を「マイニング(採掘)」と呼びます。
総発行量が決まっている
法定通貨の場合、総発行量に制限はありません。インフレが進むと、実質的に通貨の価値が下がり、過去に1万円で購入できたものが、将来には2万円出さなければ購入できないという可能性もあり得ます。
それに対し、ビットコインでは、総発行量が「2,100万BTC」と定められています。次第にマイニング報酬が減少していく仕組みであり、無制限に発行されるわけではありません。ゴールド(金)の埋蔵量に限界があるように、ビットコインの総量も決まっているため、インフレに対する耐性があります。
ビットコインの活用事例
以下、ビットコインの主な活用事例を3つ紹介します。
実店舗やECサイトにおける支払手段
一部の実店舗やECサイトでは、ビットコインで商品・サービスの購入が可能です。
ただし、取引量が増加している状況では、取引手数料が高騰し、取引が完了するまでに時間を要することがあります。これは「スケーラビリティ問題」と呼ばれており、「ライトニングネットワーク(ブロックチェーンの外部で取引を処理する技術)」の普及によって解決することが期待されています。
資産運用の手段
株式やゴールドなど、以前から投資対象とされてきたアセットクラスに加えて、近年、ビットコインをポートフォリオに組み込むケースが増えています。
ビットコインにはインフレ耐性があることから、長期的には価格上昇が見込まれる傾向にあります。そのため、インフレに備えて、資産の一部をビットコインで保有することも選択肢です。
ビットコイン準備金
現在、ビットコインを準備金として蓄えることを議論・検討・実施している国家がいくつか存在します。
例えば、アメリカでは、トランプ大統領が「戦略的ビットコイン準備金」制度を設立する旨の大統領令に署名しました。これは、刑事・民事事件で押収したビットコインを政府備蓄として保有する制度であり、予算を組んで購入するわけではありませんが、今後は、民間だけではなく、国・政府によるビットコインの活用が広まる可能性があります。
ビットコインの歴史と価格推移
過去の歴史・価格動向を振り返ることは将来を予測する上で有用です。以下、ビットコインの誕生から現在に至るまでの歴史を紹介します。
誕生から2017年末・2018年初頭の暗号資産バブルまで
2009年1月にビットコインの最初のブロックが生成され、2010年5月に初めて支払手段として利用されました。当初はごく一部の愛好家のみが興味本位でマイニングしている状態でしたが、次第に非中央集権的な仕組みに対する評価が高まり、マイニング・売買する人数が増加していきました。
ところが、2014年にビットコイン取引所「マウントゴックス」が破綻し、しばらくの間、価格が低迷します。しかし、2017年になると日本国内でもビットコインをはじめとする暗号通貨の存在が注目され価格が急騰、「暗号資産バブル」が発生しました。年末にはビットコイン価格は、1BTC=230万円を超える水準にまで到達しました。
バブル崩壊後から現在に至るまで
2018年1月中旬あたりにバブルは崩壊し、しばらく価格が低迷する時期が続きました。2020年になると上昇傾向が見られましたが、新型コロナウイルス感染症のパンデミック(世界的流行)による社会不安から急落、その後は各国の金融緩和策などの影響もあり回復、年末には価格が急激に上昇し、最高値を更新します。
途中で一時的に下落する局面がありつつも、2021年後半まで上昇トレンドが続きました。この2度目の「バブル」と形容される状況が発生した原因・背景としては、NFTやDeFiなど、新しい技術・仕組みが登場し、業界全体が盛り上がっていたことが挙げられます。
その後、2022年末に大手暗号資産取引所「FTX」が破綻し、再び価格低迷期に突入します。しかし、2024年に入ってから上昇トレンドに転換し、トランプ大統領が「戦略的ビットコイン準備金」制度を設立する旨の大統領令に署名したこともあり、2025年7月には1BTC=1,800万円を超える水準まで価格が上昇しました。
ビットコインは今後どうなる?
将来的に価格がどのくらいまで上昇するのかを正確に予測することは誰にもできませんが、長期チャートを眺めると右肩上がりの傾向が見て取れます。アメリカの戦略的ビットコイン準備金など、暗号資産業界全体にとってプラスの材料が出てきているため、今後も価格が上昇する可能性が高いでしょう。
ただし、短期的には、さまざまな要因(大手暗号資産取引所の破綻など)により、価格が下落することもあります。短期間で売買を繰り返すのであれば、損失を被るリスクも考慮し、余剰資金の範囲内でトレードすることが重要です。
ビットコインの課題
ビットコインの課題としてスケーラビリティ問題があり、トランザクションの量が増えると取引手数料が高騰し、完了までに時間がかかります。ただし、ライトニングネットワークの普及によって解消されることが期待されています。
法規制の動向も注視するべきです。マネーロンダリング防止のための法規制は年々強化されています。犯罪を防止する上で必要ではあるものの、「本人確認実施によって利便性が損なわれ、利用者が減少する」など、規制の内容によっては実利用を阻害する方向に作用する面があるかもしれません。また、マイニングに大量の電力が必要なため、環境負荷の面でも懸念が指摘されています。
まとめ
ビットコインには課題もありますが、近年、支払手段・資産運用といった形での活用が進んでいます。アメリカでは、トランプ大統領が、ビットコイン準備金制度の創設に関する大統領令に署名しました。今後、新たな技術・サービスが登場すれば、さらに実利用が進むでしょう。
ビットコイン価格は長期的には上昇傾向にあり、これからも価格が上がることが期待されます。ただし、一時的に下落する局面もあるので、余剰資金の範囲内で投資しましょう。



 地図
地図