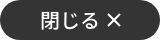非認知能力とは?幼児・小学生におすすめの非認知能力を鍛える遊び4選を紹介

「非認知能力ってよく聞くけど、どんな力? なぜ注目されているの?」
「認知できない力なら、鍛えることってできないの?」
非認知能力について、このような疑問を持つ方も多いでしょう。
非認知能力は、幼児期から9・10歳ごろまでに鍛えておくとよいといわれています。
その理由は、幼少期は脳の発達がもっとも活発な時期であり、9・10歳という年齢は思考力や表現力の土台が完成する年齢だからです。
さらに、非認知能力は、日々変化する現代社会を生きていく上で必要不可欠であることも理由といえます。
つまり、非認知能力を鍛えることは、子どもたちの未来や可能性を広げることにつながるのです。
そこで本記事では、注目を集めている非認知能力について解説し、非認知能力を鍛えられる子ども向けの遊びを紹介していきます。
非認知能力とは?
ここでは、非認知能力とは具体的にどんな力を指すのか、なぜ非認知能力が注目されているのかを解説します。
非認知能力とは具体的にどんな力?
非認知能力は、数値化がしにくい内面的な能力・スキルのことをいい、子どもがよりよい人生を歩む上で大切な力といわれています。
具体的には、「目標を決めて取り組む」「意欲や興味を持つ」「新しい発想をする」「周りの人と円滑なコミュニケーションをとる」などの力です。
問題解決能力・コミュニケーション能力・主体性・共感性・自己肯定感など、さまざまな内面的な能力が非認知能力にあたります。
参考:中央教育審議会 初等中等教育分科会|幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会 ―第2回会議までの主な意見等の整理―
なぜ非認知能力が注目されているの?
非認知能力が注目されているのは、科学やAIが発達してきたことが要因としてあります。
これまでの社会は学力・学歴重視の、認知能力を評価する社会でした。
しかし現代社会は科学技術やAIが発達し、ルーティンワークや文書作成など、定型作業的な仕事はロボットやAIに置き換わるようになってきています。
このような変化の中で、創造力や人間だからこそ可能な温かみのある対応など、「機械にはできないこと」ができる人材が求められるようになりました。
この「機械にはできないこと」を成す力が、まさに非認知能力なのです。
非認知能力は鍛えられる?
ここでは、現代社会を生き抜く力の非認知能力を鍛えることができるのか、そして、鍛えるのに適した年齢はいつなのかを解説していきます。
非認知能力は鍛えられる
非認知能力を鍛えることは可能です。
小学生から高校生の期間には、遊びや学校生活、部活動、友達との交流の中で、コミュニケーション力、問題解決能力、想像力などを鍛えられます。
社会に出てからも、仕事に取り組む際に目標設定をしてみたり、自身の発言や価値観の振り返りをしたりする中で、鍛えていくことが可能です。
非認知能力は、生涯にわたって鍛えられる力だといえるでしょう。
非認知能力を鍛えるのに適しているのはいつ?
生涯にわたり鍛えることができる非認知能力ですが、幼少期から9・10歳ごろまでに鍛えておくとよいとされています。
その理由は、幼少期は脳の発達がもっとも活発な時期であること、9・10歳の頃は思考力や表現力が備わってくるため、非認知能力を伸ばしやすいからです。
また、非認知能力は変化の大きい社会を生き抜くために必要な力であるため、社会に出るまでに鍛えておくことが重要です。
一部では非認知能力を性格と捉える研究もあります。
その研究では、性格は幼児期から学童期に形成されるため、非認知能力も幼児期から児童期に鍛えるのが重要であると報告されています。
参考:国立教育政策研究所(2017年)「非認知能力」の諸問題)
【幼児・小学生向け】非認知能力を鍛える遊び
ここでは、非認知能力を伸ばしやすいとされる幼児・小学生向けの、非認知能力を鍛える遊びを紹介します。
遊びのジャンルは以下の4つです。
- 五感に刺激を与える遊び
- 想像力を働かせる遊び
- 工程や工夫を考える遊び
- 交流を持つ遊び
具体的にどんな遊びがあるのか、詳しく見ていきます。
五感に刺激を与える遊び
五感に刺激を与える遊びは、主に子どもの感情や好奇心、想像力、問題解決能力を鍛えられます。感覚が敏感な小学校入学までの時期におすすめです。
具体的には、水遊びや泥遊び、砂遊び、草遊びなど、自然と関わる遊びがよいでしょう。
水遊びの場合は、手に触れたときの感覚が刺激になるだけでなく、水を使ってどんなことができるかを考えるのも、想像力を鍛えることに役立ちます。
泥遊びや砂遊びでは、遊ぶことを通して創造力や問題解決能力を鍛えられるでしょう。土や砂の状態で作れるものを工夫したり、うまく作れないときにどうするかを考えたりすることが、非認知能力を鍛えてくれます。
草遊びは、草相撲や、草かんむりや花かんむりを作る遊びです。草花に触れることで、好奇心を養ったり感情を育んだりと、さまざまな非認知能力を鍛える効果があります。
想像力を働かせる遊び
想像力を働かせる遊びは、コミュニケーション能力や問題解決能力、表現力を伸ばすことが可能です。
具体的には、読書、絵本の読み聞かせ、お絵描き、ごっこ遊びが挙げられます。
読書や読み聞かせでは、場面を想像したり登場人物の気持ちを考えたりすることで、コミュニケーション能力が養われます。
挿し絵とストーリーの内容を結び付けるには集中力や思考力も必要です。
語彙の強化もできるので、多方面への効果が期待できる遊びです。
お絵描きは、想像力を鍛えるだけでなく、集中力や創造力、表現力を高める効果があります。
色を変えてみたらどうなるか、画材を変えてみたらどうなるか、どんな大きさで描こうかといった具合に、好奇心も刺激します。
ごっこ遊びは、表現力やコミュニケーション能力を伸ばせる遊びです。
自分が「別の誰か」になることで、物事を多角的に見る力や思考力も養われるでしょう。
また、ごっこ遊びをすることで「お母さんはこのような役割の人」「お店の人はこんなことをする人」と、社会にどんな役割の人がいるのかを理解することにもつながります。
工程や工夫を考える遊び
工程や工夫を考える遊びは、創造力や集中力、問題解決能力などを養えるでしょう。
具体的には、積み木や工作、ボール遊びがあります。
積み木は、分類を考えたり並べたり、何かの形を作ったりする以外にも、さまざまな遊び方ができます。
積み木を観察する力や数・形への興味を養うことができ、ブロックを触れる年齢から始められる遊びです。
指先運動としても効果の期待できる遊びです。
工作は、家にあるもので作れるものを考え、完成までやりきることを通し、創造力や集中力、やり抜く力を鍛えられます。
工作の過程で思ったようにならない場合も、観察力や問題解決能力を鍛える機会といえるでしょう。
すぐに手助けをせずに、危ないときはすぐに助けに入れるように目の届くところで、様子を見守ってみてください。
ボール遊びは、蹴って遊んだり、遠くまで投げて遊んだり、キャッチボールをしたりと、さまざまな遊び方ができます。
遊び方を考えることで想像力を鍛えられます。
ほかの子どもと遊ぶことで、相手を思いやる気持ちやコミュニケーション能力なども養えるでしょう。
交流を持つ遊び
交流を持つ遊びは、コミュニケーション能力を鍛えるだけでなく、問題解決能力や社会性を養うことにもつながります。
具体的な遊びには、公園遊びや連想ゲーム、ボードゲームがあります。
公園遊びには砂遊びや草遊びなどの自然と触れ合う遊びも含まれますが、遊んでいるときに友だちに出会ったり、一緒に公園に行ったりする場合もあるでしょう。
その場合、一人で遊んでいると養われにくいコミュニケーション能力や協調性を養えます。
また、公園にある遊具を使って遊ぶことは、体力をつけたり、友だちと一緒に楽しむにはどうすればいいか考えたりと、さまざまな力をつけていける遊びです。
連想ゲームやボードゲームでは、コミュニケーション能力だけでなく、集中力や思考力も高められます。
また、ルールの中で競うことは、問題解決能力を鍛えるのに最適といえるでしょう。
まとめ
非認知能力は、想像力や社会性、やり抜く力や問題解決能力などの数値化できない力です。
これらの力は、移り変わりの激しい現代社会を生き抜くために必要な力といえます。
非認知能力は鍛えることができ、大人になってからも生涯伸ばせる力です。
しかし、変化の大きい社会を生き抜くために、脳の発達が一番大きい幼児期や思考力が備わってくる小学生の頃から非認知能力を鍛えることが重要です。
多くの子どもたちが社会で困らず、よりよい人生を歩んでいけるように、非認知能力を鍛える遊びを取り入れてみてください。



 地図
地図