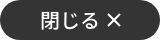リメディアル教育とは?実施内容と大学での実施例を紹介

リメディアル教育とは、学習に遅れのある学生を対象とした補習教育のことです。日本では主に大学で実施され、大学教育を受けるために必要な基礎学力を補うことを目的としています。
この記事では、リメディアル教育の定義や種類をわかりやすく解説します。大学での実施例も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
リメディアル教育について関心のある方や、大学での学習サポートについて知りたい方のお役に立てれば幸いです。
リメディアル教育の定義

リメディアル教育とは、学習に遅れがある学生に対して、基礎学力を補う目的で行われる教育です。「日本リメディアル教育学会」ではリメディアル教育を「学習・学修支援」と定義しています。文部科学省では、「大学教育を受ける前提となる基礎的な知識等についての教育」のことを指し、「補習教育」とも呼ばれています。
日本では最近になって注目を集めているリメディアル教育ですが、アメリカやフランス、カナダといった海外の大学では、以前から一般的に実施されている教育プログラムです。
日本におけるリメディアル教育は、英語や数学、国語といった基礎科目の学力を再構築し、大学での学びに備えるための重要な役割を担っています。リメディアル教育を受けることで、学生はほぼ同じ学力レベルから大学の授業をスタートでき、より効率的に学びを深めることができます。
このように、リメディアル教育は、教える側と学生の双方にとってメリットが大きいプログラムと言えるでしょう。
リメディアル教育が必要とされる2つの要因
日本でリメディアル教育が必要とされる背景には、大学入学者の学力レベルの格差が挙げられます。ここでは、学力に差が生まれる2つの要因を取り上げます。
入試の多様化による学力格差
リメディアル教育が必要とされる背景には、入試制度の多様化がもたらした学力格差があります。特に、AO入試や推薦入試を通じて合格する学生は、一般入試で学力を測る機会がありません。これにより、学力にばらつきが生じ、習熟度の低い学生が大学に入学するケースが増えています。
実際、2020年に文部科学省が実施した英語の入試方法の調査によると、全体の約半数近くの学生が一般入試以外の方法で入学しています。
このように、入試の多様化が進んだ結果、学力に差がある学生が増え、リメディアル教育によって基礎学力を補う必要性が高まっているのです。
大学全入時代による学力格差
リメディアル教育が必要とされる背景として、少子化の影響も挙げられます。近年、18歳人口の減少が進む中、定員割れを起こす大学が増加しています。2024年度にはついに、入学希望者の総数が入学定員の総数を下回る「大学全入時代」に突入しました。
大学別に見ると、国公立大学の定員充足率は104%であったのに対し、私立大学の充足率は97%でした。「日本私立学校振興・共済事業団」の調査によると、2024年度には私立大学の6割が定員割れを起こしています。
大学を選ばなけば大学進学できる状況では、学生の学習意欲も低下するため、学力レベルに差が生じ、リメディアル教育が必要となってくるのです。
リメディアル教育の4つの種類
ここでは、現在日本の大学で実施されているリメディアル教育の種類を4つご紹介します。
高等学校までの基礎教育復習型
1つ目は、高校までの基礎教育を復習するタイプです。大学入学後に習熟度テストを行い、個々の学生の学力レベルに合わせて補習が行われます。
中には、入学直後に全学生に対してリメディアル教育を実施する大学もあり、リメディアル教育が必修科目となっている場合もあります。
大学の専門課程教育の基礎学習型
2つ目は、専門的な大学教育に必要な基礎知識を補うタイプです。理学や工学など、高校では科目がない分野を学ぶ大学では、専門的な授業に進む前に、リメディアル教育で基礎知識を補います。
多くの場合、入学当初や大学1年次に全学生に向けて行われることがほとんどです。
最近増えてきている「文理融合学部」で、授業の導入としてリメディアル教育を実施するパターンも見られます。
大学教育の学習支援型
3つ目は、大学教育の学習支援型です。このタイプのリメディアル教育では、学生支援センターや学習支援室などの専門組織が授業外で補習を行います。
特徴は個別サポートができるところです。全学生に対して一斉に行われる授業とは異なり、一人ひとりの学力レベルに合わせて必要な支援が提供されます。
このような学習支援サポートは、学生の学習面での相談役としての機能も果たしています。
大学入学前教育型
リメディアル教育には、大学入学前に実施されるものもあります。多くは、AO入試や推薦によって早期に入学が決まった学生を対象として行われます。
レポートや通信教材を使って、入学前に自宅で学力を補うだけでなく、学生の学習意欲を保つ役割もあります。
リメディアル教育をオンライン学習で行う2つのメリット
リメディアル教育の手法として、インターネットを使ったオンライン学習が注目を集めています。ここでは、対面授業では得られない2つのメリットをご紹介します。
コストがかからない
オンライン学習の1つ目のメリットは、コストがかからないことです。
学習の遅れは学生によって差があるため、習熟度別に授業を行う必要があります。対面授業の場合、授業ごとに教員や教室を用意しなければなりませんが、オンライン学習にすれば、録画した授業を繰り返し使うことができます。
このように、リメディアル教育をオンライン学習にすることで、コストを大幅に削減することができるのです。
個々のレベルに対応できる
2つ目のメリットは、個別学習に最適な「e-ラーニング」を活用できる点です。
e-ラーニングでは、学生の学習履歴や成績をインターネット上で一元管理できます。そのデータをもとに、学生一人ひとりの習熟度に合わせた補習を行うことができ、より効果的な学習支援が可能となります。
リメディアル教育の実施大学3選
日本でもリメディアル教育を実施する大学が増えてきています。ここでは、種類の違うリメディアル教育の実施例を3つご紹介します。
弘前大学
弘前大学では、全学年の学生を対象とした数学・物理(電磁気学/力学・熱力学・波動)・化学のリメディアル教育を実施しています。
学生は、自分が必要だと思う単元だけ、無料で何コマでも受講できます。これにより、効率的に苦手分野の克服や復習ができ、自分のやりたい専門的な研究をスムーズにスタートできるでしょう。
武蔵野大学
武蔵野大学の工学部環境システム学科は、先ほどご紹介した「文理融合学科」の実例です。
当学科では文系出身者も多いため、物理・化学・数学の各科目について4つのクラスに分けてリメディアル教育を実施していました。
現在はICT教材を活用し、さらに個別最適化されたリメディアル教育が行われています。
宇都宮大学
宇都宮大学では、AO入試や推薦入試で合格した学生を対象に、入学前にリメディアル教育を実施しています。
高校との連携のもと、課題図書に対するレポート作成や課題提出を実施して、大学教育へのスムーズな移行をサポートしています。
まとめ

リメディアル教育は、高校までの学習の遅れを取り戻し、大学での学びをスムーズに進めるために非常に重要です。高校との連携を強化することで、さらにその効果を高めることができます。
さらに、オンライン学習やAIの活用で、学生一人ひとりに合わせたサポートが可能になり、学習意欲の向上にも繋がっています。
今後、日本の大学におけるリメディアル教育の重要性は高まり、各大学の取り組みにますます期待が寄せられるでしょう。



 地図
地図