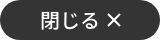人事業務にAIを導入するメリット・デメリットは?活用事例も紹介

近年、AIの発達に伴い、人事業務にAIを取り入れる企業が増えています。
しかし、人事は業務の幅が広く、どの業務にAIをどう活用すればいいのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、人事業務にAIを導入するメリットやデメリット、活用事例などについて解説します。
人事領域へのAI導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
人事業務でAIが注目される理由
人事業務においてAIが注目を集める背景には、社会構造や企業経営の変化があります。
特に日本では少子高齢化が進み、労働人口が減少しており、採用競争は今後さらに激化していくと考えられます。
限られた人材を確保し、育成・定着につなげるには従来のやり方では限界があり、その解決策としてAIが注目されているのです。
また、人事業務は採用や評価、人材配置、育成、労務管理など多岐にわたり、それぞれに膨大なデータ処理や判断が求められます。
従来は人間の経験や直感に頼っていた部分も、AIを活用して業務を効率化しようとする企業が増えています。
人事業務にAIを導入するメリット
人事業務にAIを導入するメリットは、主に下記3つです。
- 業務効率化が期待できる
- 人間によるバイアスを減らせる
- 膨大なデータを効果的に活用できる
AIは、膨大かつ多様なデータを高速に処理し、人間では見落としがちなパターンや相関関係を明らかにします。
人事担当者は単純作業から解放され、より戦略的な業務に集中できるでしょう。
業務効率化が期待できる
AIは、採用や労務管理、評価業務などにおける定型作業を自動化し、業務スピードや質を高めます。
AIを活用すれば、応募者情報の入力や残業時間の管理、有給取得状況の分析など、これまで時間がかかっていた作業を自動化できます。
担当者が人間ならではのコミュニケーションが必要な業務に、より多くの時間を割けるようになり、人事部門の業務効率化につながるでしょう。
人間によるバイアスを減らせる
採用や評価業務など、判断力が大切な業務において、AIの活用で人間によるバイアスを減らせます。
人事業務においては、担当者の経験や価値観が判断に影響する場合があります。
AIは事前に定義された評価基準やデータ分析結果をもとに判断を行うため、人間のように感情や先入観などのバイアスに左右されることはありません。
AIの判断も学習データに依存するため、データに偏りがないかチェックが必要ですが、効果的に使用すれば客観的な判断が得られるメリットがあります。
膨大なデータを効果的に活用できる
AIを活用することで、人事部門の膨大なデータを効果的に活用できるメリットもあります。
人事部門には、採用履歴や勤怠記録、評価データなど、膨大な情報が蓄積されています。
人間が分析して有効活用するのは難しいですが、AIであればデータを高速で処理し、相関関係や傾向を明らかにすることが可能です。
これまで使われていなかったデータが企業の戦略的資産になるため、組織全体のパフォーマンス向上や人材の定着などにつながります。
人事業務にAIを導入するデメリット
人事業務にAIを導入するデメリットは、主に下記3つです。
- 導入するためにコストがかかる
- ブラックボックス化する可能性がある
- プライバシーとセキュリティにリスクがある
AIを導入する際にメリットばかりに注目して安易に導入すると、コスト面や運用面で思わぬ問題が発生する可能性があります。
特に、人事業務は企業の根幹に関わるため、システムの信頼性や透明性、セキュリティなど、さまざまな視点からリスクを把握することが重要です。
導入するためにコストがかかる
AIシステムの導入には、初期費用と運用コストの両方が発生する場合が多いです。
初期費用には、システムのライセンス購入や既存業務との統合、カスタマイズなどが含まれます。
また、導入後もシステム保守やアップデートなどに継続的な費用がかかるため、運用コストも事前に検討する必要があります。
AIを効果的に使いこなすためには、担当者や関係部門への教育・研修も必要になるため、ROI(投資対効果)を事前に見積もることが重要です。
ブラックボックス化する可能性がある
AIは複雑なアルゴリズムで動作しており、判断するプロセスが人間にとって理解しづらい場合があります。
人事の意思決定において、なぜその結果になったのか説明できない状態は、従業員や応募者からの信頼を損なう要因となります。
ブラックボックス化を防ぐためには、AIの判断基準や利用方法を社内外に明確に説明できるようにしておくことが重要です。
また、AI導入時には、ブラックボックス化のリスクを軽減するための運用ルールや監視体制を整える必要もあります。
プライバシーとセキュリティにリスクがある
AIを活用するためには、大量の人事データを収集・保存・分析する必要があるため、プライバシーやセキュリティ上のリスクが高まります。
人事データには、氏名や住所、経歴など、機密性の高い個人情報が多いです。
もしサイバー攻撃や不正アクセスによって情報が流出すれば、法的責任や社会的信用の低下につながります。
暗号化やアクセス制限、定期的なセキュリティ監査など、プライバシー保護と情報セキュリティに関する技術的・組織的な対策を徹底しましょう。
人事業務におけるAI活用事例
AIの人事領域での活用は年々広がっており、採用や評価だけでなく、従業員エンゲージメントの向上など、幅広い分野で成果が出ています。
AIは膨大なデータを高速で処理し、時間と労力がかかる作業を効率化するだけでなく、精度の高い分析や予測を可能にします。
今回は具体的な4つの活用事例を紹介します。
採用プロセスの自動化
採用プロセスにおいて、履歴書や職務経歴書、ポートフォリオなどの応募書類をAIが自動で解析し、職務要件とのマッチ度をスコア化することが可能です。
担当者は書類選考にかかる時間を大幅に短縮でき、候補者の精査や面接対応など、人的な判断やコミュニケーションが求められる業務に注力できます。
ソフトバンクではAIを活用した動画選考が新卒採用で導入され、吉野家ではAIによる対話形式の面接も実施されています。
また、チャットボットによる応募者対応も進化しており、求人情報の提供や面接日程の調整、応募状況の確認などの問い合わせに24時間対応可能です。
AIを適切に活用することで、採用のスピードと精度の向上が実現されています。
データに基づいた適切な人材配置
AIは従業員のスキルや経歴、評価データなどを総合的に分析し、最適な人材配置をサポートします。
サイバーエージェントでは、本人の希望や適性情報などをAIが分析し、活躍する可能性が高い部署を提案する配属マッチングシステムを導入しています。
また、AIは過去の成功事例や異動後の成果データを学習し、配置の成功確率を予測することも可能です。
人事担当者は経験や勘だけに頼らず、客観的な根拠に基づいて人事判断を行えるようになります。
従業員のエンゲージメント分析
従業員のエンゲージメントは、組織の生産性や離職率に関わる重要な指標です。
AIは、定期的なアンケート結果や社内SNS、勤怠データなどを分析し、従業員のモチベーションや職場満足度を可視化できます。
Googleでは、従業員のアンケートの自由記述欄に対し、AIを活用して感情分析や「なぜそう感じたか」の原因を抽出しています。
AIをエンゲージメント分析に活用することで、離職の兆候やチームの士気低下を早期に発見し、適切な対策を講じることが可能です。
勤怠管理の効率化
AIを活用すれば、勤怠データをリアルタイムで分析し、異常値や不正の可能性があるデータを即座に検出できます。
NECは、自社の顔認証技術を既存の勤怠管理システムと統合し、不正打刻を防止するソリューションを提供しています。
また、AIは過去の勤怠パターンを学習し、長時間労働のリスクを予測できるため、事前に人事担当者へ警告を出すことが可能です。
AIを活用すれば、労務管理の質を高めつつ、従業員の働き方改善も実現できるでしょう。
まとめ
少子高齢化や人手不足により、人事業務においてAIを活用した業務効率化や質の向上の重要性が高まっています。
近年では、採用や育成、人材配置、評価など、幅広い領域で人事AIを導入する企業が増えており、今後もその流れは加速すると考えられます。
この記事で紹介した内容を参考に、人事AIを効果的に活用し、人事業務の効率化と組織力の向上を実現してみてください。



 地図
地図