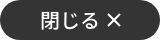教育現場で注目のゲーミフィケーションとは?実践事例と活用のポイント3選

近年、主体的で能動的な学びを促すために実践されてきた「アクティブラーニング」とともに、「ゲーミフィケーション」という言葉が使われるようになってきました。ゲーミフィケーションは教育やビジネスでとられている手法で、学習意欲や行動の継続性を高めることが目的です。教育現場では、非認知能力の育成やアクティブラーニングとの組み合わせによって、子どもたちの主体的な学びを促す事例が増えています。
本記事では、ゲーミフィケーションの基本的な考え方から、教育現場での活用事例、ゲーミフィケーションを実践する上で教育者が意識すべきポイントを紹介します。
ゲーミフィケーションの事例に興味がある人は、ぜひ読んでみてください。
ゲーミフィケーションとは?
ここでは、ゲーミフィケーションの考え方と、教育分野との関連性を解説していきます。また、これまでよく聞かれていたアクティブラーニングとの違いもまとめました。
ゲーミフィケーションとは?非認知能力との関係性
ゲーミフィケーションとは、ゲームに含まれる「報酬」「達成感」「競争」「協力」などの要素を、教育やビジネスなどの分野に応用する考え方です。このように聞くと「ゲーム」を連想しがちですが、あくまでも「ゲームの要素を取り入れる」ことがポイントです。ゲーミフィケーションは、子どもたちの興味や関心を引き出し、継続的な学びを促す目的で、教育現場での導入が進んでいます。
ゲーミフィケーションは非認知能力との関係でも注目されています。非認知能力とは、自己肯定感や協調性、粘り強さなど、テストでは測れない力のことです。子どもたちはゲーミフィケーションを通して、挑戦・達成のサイクルを繰り返し、非認知能力を育んでいくことができます。
アクティブラーニングとの違い
ゲーミフィケーションとアクティブラーニングはどちらも子どもたちが主体的に学ぶことを目指していますが、アプローチが少し異なります。アクティブラーニングは、ディスカッションやグループワークなどを通じて知識の定着と応用力を高め、子どもたちの主体的で対話的な学びを目指す手法です。
一方、ゲーミフィケーションは「楽しい」といった学習への動機づけや、行動変容に重点を置いています。子どもたちが自ら進んで課題に取り組めるよう、報酬や達成感を得られる仕組みを作り、学習意欲を高める手法です。
つまり、アクティブラーニングが学習の仕方に焦点を当てるのに対し、ゲーミフィケーションは学習したいと思わせる仕掛けづくりに重点を置いているのです。
ゲーミフィケーションと教育の関係性
ゲーミフィケーションは、子どもたちが学習に興味・関心を持ち、学習に対しモチベーションを維持するために切り離せない関係にあります。
現代社会はAI技術が発達し、子どもたちが目にするコンテンツは自動的にピックアップされるようになったため、自ら興味・関心を育む機会が減少しています。ゲーム的要素を取り入れて自ら課題に取り組めるようにすれば、さまざまな興味や関心を刺激し、学習意欲の向上や学習習慣の定着にもつながるでしょう。
教育現場でのゲーミフィケーション活用事例
ここでは、実際の教育現場でどのようにゲーミフィケーションが取り入れられているのか、以下の3つの項目に分類し、紹介します。
- プログラミングや探求学習
- 学級活動や校内活動との連動
- デジタルツールを活用した実践
詳しく見ていきましょう。
プログラミングや探求学習
プログラミングの分野では、遊び要素の強い教材が活用されています。例えば、小学校低学年の授業では、ゲーム感覚でコードを書けるScratchが活用されています。ゲームを通して自然と論理的思考力や問題解決力を養える点が特徴です。
探求学習や総合学習の時間にもゲーミフィケーションを取り入れている学校が増えてきました。実践事例ではミッションとして課題を提示したり、成果に応じてポイントを与えたりして、生徒の探究心を刺激する仕掛けが盛り込まれています。ポイントの獲得によって成果を可視化するのも仕掛けのひとつと言えるでしょう。成果が目に見えることで、子どもたちは自分の考えや行動に自信を持てるようになります。
学級活動や校内活動との連動
ゲーミフィケーションは、日々の生活指導や学校行事にも応用可能です。例として、クラスで決めた行動目標が達成できたらポイントが貯まるシステムが挙げられます。クラス全体で協力してレベルアップする仕組みを導入すると、協調性や責任感を育めるでしょう。
校内イベントにもゲーミフィケーションが活用できます。スタンプラリー形式の校内探検や、クイズ大会などは、楽しみながら学びや気付きを得る絶好の機会となるでしょう。
デジタルツールを活用した実践
ICT環境の整備が進む現在では、タブレットやアプリを活用したゲーミフィケーションの事例も増えています。例えばKahoot!というアプリを使った事例では、クイズ形式で授業を進めたことで、子どもたちの集中力や学習意欲の向上が実感できたそうです。
また、授業中の行動に応じてポイントが付与できるツールもあります。Classcraftというツールで、子どもたちの集中力の維持、出席率の向上に役立っているようです。
ゲーミフィケーションの実践で教育者が押さえておきたい3つのポイント
ここでは、ゲーミフィケーションを実践する際に教育者・指導者が押さえておきたいポイントを3つ紹介します。
- ゴールを明確にする
- 「遊び」と「学び」をつなげる考え方をする
- フィードバックの質とタイミング
それぞれ詳しく解説していきます。
ゴールを明確にする
ゲーミフィケーションを実践する際には、その目的や得たい成果を明確にすることがポイントです。
さらに、ゴールとなる目標を達成するために必要なことを見極め、中目標や小目標も設定すると、子どもたちのやる気を刺激できます。きちんとしたシナリオ設計は必要ですが、目標の一部を子どもたち自身に設定させるのも効果的です。そうすることで、達成感や責任感が生まれ、学習習慣の定着も期待できるでしょう。
「遊び」と「学び」をつなげる考え方をする
ゲーミフィケーションを教育に取り入れる際、最も重要なのは「遊び」と「学び」をつなげる考え方をすることです。子どもたちを楽しませることばかりを考えてしまうと、本来の目的である子どもたちの主体的な学びを促す働きが弱まってしまいます。
具体的には、ゲーム的な報酬を与えるだけでなく、なぜその行動が評価されるのか、どうすれば次のステップに進めるのかといった学習の意味づけを明確にしましょう。そうすることで、子どもたちの好奇心や達成感が学びにつながりやすくなります。
フィードバックの質とタイミング
フィードバックの質とタイミングも、押さえておくべきポイントです。質の高いフィードバックは子どもたちに自信を与え、迅速なフィードバックはモチベーションの維持や向上につながります。
フィードバックの内容は、肯定的で個別的かつ具体的な内容を心がけましょう。より良くするための改善点があれば、子どもたちに考えさせるような問いかけを盛り込むことがおすすめです。
単純な正解・不正解のフィードバックよりも、子どもたちの自信ややる気の向上を促してくれるでしょう。
まとめ
ゲーミフィケーションは単なる遊びではなく、学習意欲を高めるための手法のひとつです。
アクティブラーニングと同様に、子どもたちが主体的に学ぶことを目指していますが、その手法は異なります。アクティブラーニングは学習内容の深い理解や学び方に重点を置いた手法であるのに対し、ゲーミフィケーションは学習意欲や継続性を高めるための手法です。
ゲーミフィケーションにはさまざまな事例があるため、教育者がその目的を理解し適切に活用することが重要です。子どもたちが現代社会を生き抜く力を養うためにも、ゲーミフィケーションを試してみてください。



 地図
地図