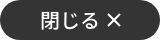今注目の「ウェルビーイング教育」とは?学校現場での効果と取り組み事例を紹介

「ウェルビーイング教育はどのような意味なのか」
「教育現場での効果や具体的な事例を知りたい」
近年、注目されているウェルビーイング教育について、上記のように悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
ウェルビーイングは心と体、そして人とのつながりがバランスよく満たされた持続的な幸福のことです。現代社会では不登校やいじめなど、子どもが抱える悩みが多様化しています。一人ひとりのウェルビーイングを高めるためには、教育現場から豊かな心を育むことが大切です。
本記事では、ウェルビーイング教育について詳しく解説するとともに、具体的な効果や実際の取り組み事例を紹介します。ウェルビーイング教育を詳しく知りたい方、教育現場での取り組み方法を知りたい方は参考にしてください。
ウェルビーイング教育とは
そもそもウェルビーイングとは、身体的・精神的・社会的に満たされている状態のことです。近年では教育にもウェルビーイングが重要とされ、子どもの幸福や心の健康を第一に考えた学校づくりや、ストレスの少ない学習環境が求められています。
ウェルビーイングを構成する5つの要素
ウェルビーイングを構成する5つの要素は次のとおりです。
l Positive Emotion:ポジティブ感情
l Engagement:エンゲージメント
l Relationships:人間関係
l Meaning:意味
l Achievement:達成
アメリカの心理学者、マーティン・セリグマン氏が提唱した要素で、頭文字をとり「PERMA(パーマ)の法則」と呼ばれています。
5つの要素がバランスよくとれていると、より充実した人生を送れるとされています。
文部科学省による位置付け
文部科学省では「第4期教育振興基本計画(令和5年度~9年度)」において、日本社会に根差したウェルビーイングの向上が掲げられています。
教育振興基本計画での主要なコンセプトは以下2つです。
l 持続可能な社会の創り手の育成
l 日本社会に根差したウェルビーイングの向上
現代社会を生きる子どもたちは、自ら社会をよりよくしていく力が求められます。そのためには、教育の中で主体性や問題解決能力、表現力などをバランスよく育てることが大切です。
また、一人ひとりが幸せを感じるのはもちろん、地域や社会全体も豊かになるように、教育を通してウェルビーイングを向上する必要があります。
自己肯定感や幸福感、自己実現などを育み、心と社会の両方の幸せを目指すことが重要です。
教育に関連するウェルビーイングの要素
「第4期教育振興基本計画(令和5年度~9年度)」では、教育に関連するウェルビーイングの要素を以下のようにあげています。
l 自己肯定感
l 心身の健康
l 幸福感
l 協働性
l 社会貢献意識
l 学校や地域でのつながり
l 自己実現
l 安全安心な環境
l 多様性への理解
l 利他性
l サポートを受けられる環境
子どもが学校で楽しく過ごせているか、自分に自信があると感じているかなどは、目には見えて把握できません。学力ではわからない心の声を把握し、教育に活かしていくことが大切です。
教育現場でウェルビーイングが注目されている理由
教育現場でウェルビーイングが注目されているのは、子どもの学力と幸福度が深く関わっているからだといわれています。
ここでは、ウェルビーイングが注目されている理由を詳しく解説します。
現代社会において子どもが抱える困難が多様化している
いじめや不登校、家庭環境の問題やSNSのトラブルなど、現代の子どもたちは多くの問題にさらされています。教育現場では学ぶこと以外に、一人ひとりが心身ともに安心して過ごせるような環境づくりが必要です。
子どもたちの健康を維持するために、ウェルビーイングの視点が求められています。
主体性や創造力を育む必要がある
変化の激しい社会に対応するためには、自分で考えて行動する力が重要です。
教育現場では子どもが自分の興味関心を追求し、失敗しても尊重される環境を整えることが求められます。ウェルビーイングが向上できれば、自ら学んだり何かしたいと感じたりできるため学力の育成にもつながります。
地域における学びを通じて人々のつながりを形成できる
学校と地域の連携が深まると、世代を超えたつながりや関わりがうまれます。地域全体が子どもを育てる意識をもてるようになるでしょう。
子どもも地域の中で役に立つことが実感できれば、社会貢献にもつながります。共感や協働性などウェルビーイングに深く関わる力が重要になる現代社会において、地域コミュニティの形成は重要です。
ウェルビーイング教育がもたらす効果
ウェルビーイング教育には子どもはもちろん、教育の質や教員の働きやすさなどにも効果をもたらします。ここでは主な効果を3つ紹介します。
より質の高い授業を提供できる
ウェルビーイング教育は子どもも教員も、よりよい学びの時間が共有できるため授業の質が向上します。
ウェルビーイングが高まると、子どもが意欲的に授業に参加し、自分の意見を安心して伝えられるからです。教員が一方的に授業を行うのではなく対話的に学べるため、子どもの成長につながります。
保護者と学校との信頼関係が深まる
ウェルビーイングな環境が整うと、保護者と学校の信頼関係を深められます。
ウェルビーイング教育では、学校が子ども一人ひとりの健康維持を大切にします。その結果、保護者も安心でき学校と一緒に子育てしている実感をもてるようになるからです。家庭との連携がスムーズになり、信頼関係の土台を築いていけます。
教員のストレスが軽減される
ウェルビーイングは子どもだけでなく、教員自身の働き方や心の健康にも関わる重要な要素です。ウェルビーイングが高まると教員が孤立せず、安心して働く環境を整えられます。
子どもや保護者と良好な関係を保てると、心理的負担の軽減につながります。チームとして協力しあえると、働きやすい職場になるでしょう。
ストレスが減ると教員自身のウェルビーイングが保たれます。
ウェルビーイング向上のために日常生活で取り組めること
ウェルビーイング向上のためにできることを立場別に紹介します。日常生活で実践しやすい取り組みのため、参考にしてください。
子ども
心の健康を保つために、生活リズムを整えたり、リラックスできる時間をつくったりしましょう。デジタル化が進む現代社会では、情報量が多く疲れる子どもも多くいます。自分の時間を大切にし、ストレスをためないことが大切です。
また、友だちや先生と積極的にコミュニケーションをとり、人との関わりで幸福感を得ることもウェルビーイングの向上につながります。
教員
教員は子どもとの信頼関係を意識し、安心できる環境をつくることが大切です。子どもにとってよりよい学習ができるよう、一人ひとりに寄り添う教育を実践していきましょう。子どもの安心感と信頼が高まると、学力向上にもつながります。
さらに、多忙な日々を送る教員は心と体の健康を保つことが重要です。自分自身のウェルビーイングを大切にし、働きやすい環境を職場全体でつくっていく必要があります。
保護者
子どもにとって家庭はもっとも安心できる場所です。
日常的に会話する時間をつくり、前向きな声かけをして子どもが悩みを打ち明けやすい雰囲気をつくりましょう。できないことに目を向けるのではなく、子どもの得意なことを応援し自信を育てることが重要です。
子どもが自分の気持ちや思いを受け止めてもらっていると実感できれば、心の安定が保てます。
そして、保護者自身も無理しないことが家族のウェルビーイングにつながります。
学校現場での具体的な取り組み事例
ここでは、実際に教育現場でウェルビーイングに取り組んだ事例を紹介します。
埼玉県上尾市立平方北小学校
「先生も子どもも毎日行きたくなる学校」を目指し、ウェルビーイングを学校経営の柱にしている点が特徴です。
教職員には働きやすさと主体性を、子どもたちには褒めて伸ばす教育や外遊び、児童主体の活動を通じて、安心して過ごせる環境づくりを実践しています。
学校全体で「幸せに学び・働く」文化を育てている小学校です。
富山県魚津市立星の杜小学校
星の杜小学校は「木育」に力を入れ、新校舎を設立したときには地元産の木材を使用し、子どもたちが木のぬくもりを日常的に感じられる環境を整えています。
施工時には児童が職人と一緒に塗装や木パネルづくりなどを体験し、地域と連携した取り組みを通じてウェルビーイングの向上を目指しています。
静岡県三島市立中郷小学校
勤務時間内の「ゆとり時間」を確保し、働きやすい職場環境を整備している小学校です。
業務の見える化やチームでの協力体制の強化、ICTの活用などを通じて教員の業務負担を軽減しています。担任が安心して子どもと向き合える時間をつくることで教育の質が高まり、結果としてウェルビーイングの向上にもつながっています。
まとめ
ウェルビーイング教育は学力だけではなく、心身ともに健康に生きる力を育むために重要です。子どもの学力と幸福度は深い関係があり、自己肯定感や社会とのつながりを高めることで学びの質を向上できます。
さらに、ウェルビーイングは子どもだけでなく、教員自身の働き方や心身の健康維持にも必要な要素です。実際の教育現場でも働きやすい環境を整えたり、子どもとの時間をつくったりして教育の質を高めています。
今後の教育現場では、子どもたちが幸せに自分らしく生きるための力を育む必要があるでしょう。



 地図
地図