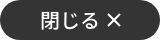暗号資産のトレードを検討している方は必見!「KYC」について徹底解説

暗号資産のトレードを実施する際には、「KYC」が必要とされます。KYCとは、顧客(になることを希望する者)の身元を事業者(金融機関など)が確認するプロセスです。マネーロンダリング防止やテロ資金供与防止を目的として、日本国の法令や国際ルール(金融活動作業部会の要請・勧告)に基づいて実施されています。
本記事では、暗号資産取引を検討している方に向けて、KYCがどのようなものなのかを詳しく解説します。KYCが実施される法的根拠・背景事情や、チェックされる事項、具体的な実施方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
KYCとは
KYC(Know Your Customer)とは、顧客の身元(氏名・住所など)を確認する手続きです。「本人確認」とも呼ばれるプロセスで、顧客側は金融機関などに対して本人確認書類などを提出(アップロード・郵送)しなければいけません。
マネーロンダリング防止(AML、Anti−Money Laundering)やテロ資金供与防止(CFT、Countering the Financing of Terrorism)を目的として、主に金融業界(銀行・証券会社・暗号資産交換業者など)で実施されています。
暗号資産取引でKYCが実施される法的根拠・背景事情
暗号資産取引サービスを提供する事業者は、日本国の法令(犯罪収益移転防止法)や国際ルール(金融活動作業部会の勧告)に基づいて、暗号資産のトレードを希望する顧客に対してKYCを実施しています。以下、根拠法令および金融活動作業部会の勧告に関して詳しく説明します。
犯罪収益移転防止法
犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)の第4条において、「特定事業者」が「特定取引」を実施する場合、KYC(取引時確認)を行わなければいけない旨が定められています。
以下は、「特定事業者」の例です。
- 金融機関(銀行・証券会社・貸金業者・資金移動業者・暗号資産交換業者など)
- クレジットカード会社
- ファイナンスリース事業者
- 宅地建物取引業者
- 宝石・貴金属取扱業者
- 郵便物受取サービス業者・電話受付代行業者・電話転送サービス業者
- 弁護士・司法書士・行政書士・公認会計士・税理士
金融機関(暗号資産交換業者を含む)に関しては、預貯金契約の締結や、200万円を超える大口現金取引、10万円を超える現金の受払いをする為替取引などが「特定取引」に該当します。
なお、上記は概略です。特定事業者の詳細や、金融機関以外の場合の「特定取引」については、警察庁の「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」などでご確認ください。
金融活動作業部会(FATF)の要請・勧告
金融活動作業部会(FATF)は、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止を目的として、各国の金融当局に対し、KYCなどを実施するための法制度の整備を求めています。FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering)とは、マネーロンダリング対策における国際協調を推進するために、1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間会合です。
当初は薬物犯罪に関連したマネーロンダリングを取り締まることが目的とされましたが、その後、薬物犯罪以外の組織犯罪・テロ行為に関連したマネーロンダリングも取り締まり対象とされました。現在、FATFには38の国・地域と2つの機関が加盟しており、年3回開催される全体会合において活動に関する事項が決定されています。
日本では、2024年4月1日に、FATFの勧告に適切に対応することを目的とする「FATF勧告対応法」が完全施行されました。なお、「FATF勧告対応法」が施行される前から、適宜、勧告への対応は進められてきました。例えば、FATFの要請・勧告を踏まえて犯罪収益移転防止法が改正されており、取引時確認の対象となる暗号資産の交換などのしきい値が200万円から10万円に引き下げられています。
暗号資産取引のKYCでチェックされる事項
200万円を超える財産の移転を伴わない取引のみ実施される場合は、取引時確認において、以下に示す事項をチェックされます。
- 顧客の氏名
- 居住地
- 生年月日
- 取引の目的
- 職業
200万円を超える財産の移転を伴う取引も実施される場合は、上記に加えて「資産・収入の状況」も確認されます。顧客側は、事業者の求めに応じて必要書類の提出などを実施しましょう。
暗号資産取引に関するKYCの実施方法
暗号資産取引に関するKYCは、対面ではなく、インターネットや郵便などによる非対面の方法で実施されるケースが一般的です。なお、非対面で実施されるKYCは、以下の2種類に大別されます。
- オンラインで完結する方法
- 郵送による書面のやり取りを伴う方法
それぞれに関して詳しく説明します。
オンラインで完結する方法
オンラインで完結するKYCは、1~4のいずれかの方法で実施されます。
- 顧客が「写真付き本人確認書類の画像」と「本人の容貌の画像」を送信する
- 顧客が「写真付き本人確認書類のICチップ情報」と「本人の容貌の画像」を送信する
- 顧客が「本人確認書類の画像またはICチップ情報」を送信したうえで、暗号資産交換業者が、金融機関またはクレジットカード会社に「本人特定事項を確認済みであること」を確認する
- 顧客が「本人確認書類の画像またはICチップ情報」を送信したうえで、暗号資産交換業者が、当該顧客の預貯金口座に金銭を振り込み、顧客が「振り込みがあったことを示すインターネットバンキング画面のスクリーンショットなど」を送信する
なお、オンラインで電子的に完結するKYCは、「eKYC(electronic Know Your Customer)」と呼ばれることがあります。
郵送による書面のやり取りを伴う方法
オンラインで完結せず、郵送による書面のやり取りを伴う方法が用いられるケースもあります。その場合は、1または2のいずれかの方法でKYCが実施されます。
- 顧客が「本人確認書類の原本の送付」「本人確認書類のICチップ情報の送信」「事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影した写真付きの本人確認書類の画像の送信」のいずれかを実施したうえで、暗号資産交換業者から送付される「転送不要郵便物」を受け取る
- 顧客が「2種類の本人確認書類の写しの送付」「本人確認書類の写し+現在の住居が記載された補完書類の原本または写しの送付」のいずれかを実施したうえで、暗号資産交換業者から送付される「転送不要郵便物」を受け取る
各事業者の公式サイトで手順の詳細をご確認のうえ、不明な点がある場合は問い合わせましょう。なお、オンラインでも郵送でも、画像が不鮮明だったり、氏名や住所などの記入をミスしていたりするとKYCが完了せず、やり直しを求められる可能性があるのでご注意ください。
まとめ
暗号資産を取引する場合、KYC(本人確認)を実施しなければいけません。KYCは、マネーロンダリング防止やテロ資金供与防止を目的として、犯罪収益移転防止法などで義務付けられています。多くの暗号資産交換業者では、オンラインで完結するeKYC(electronic Know Your Customer)を実施しています。郵便物の受け取りが不要で、スムーズにKYCを実施できることが特長です。
暗号資産は便利ではあるものの、犯罪組織によって悪用されるケースもあります。犯罪収益移転防止法を遵守し、KYCを実施することによって、クリーンな投資環境が構築されるでしょう。



 地図
地図