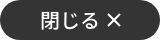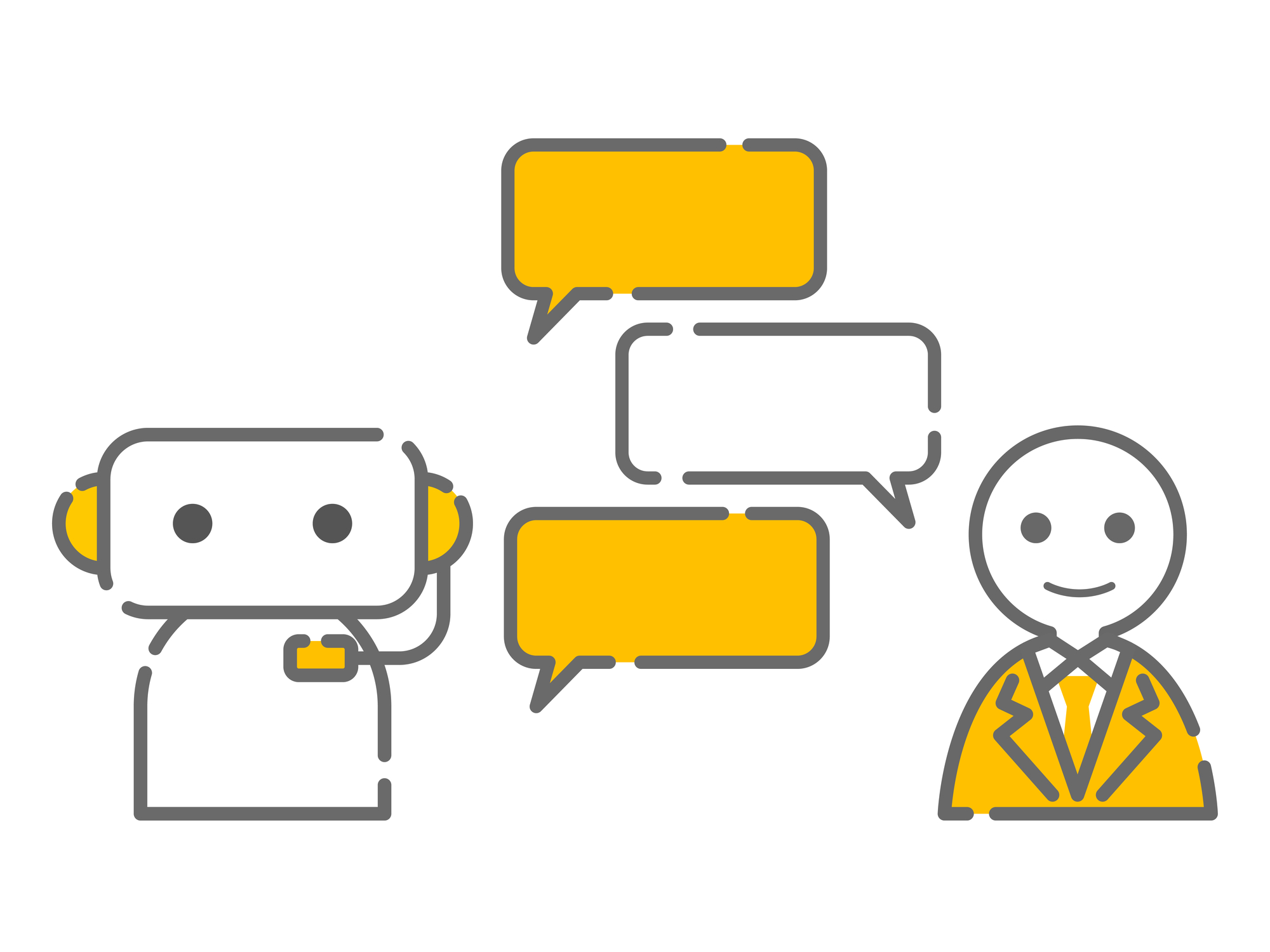教育に“ゲーム要素”を。アクティブラーニングを深めるためのヒントと実践

「子どもたちを主体的に学びに向かわせるには、どうすればいいのか?」
小学校教員として12年間、現場で子どもたちと向き合う中で、幾度となくこの問いを自らに投げかけてきました。現在の学習指導要領で重視されている「主体的・対話的で深い学び」、いわゆる“アクティブラーニング”や、教育における“ゲーミフィケーション”の考え方は、この問いへの一つのアプローチといえるかもしれません。
本記事では、教育における“ゲーム的要素”の可能性とアクティブラーニングとの関係性について、筆者の現場経験を交えながら解説していきます。
アクティブラーニングとは?現行指導要領における位置づけ
アクティブラーニングの定義と導入の背景
アクティブラーニングとは、学習者が能動的に学びに関わることを重視する教育方法です。知識の一方的な伝達ではなく、自ら課題を発見し、対話を通じて深い理解や問題解決力を養います。
2012年の中教審答申を機に広まり、2017年改訂の学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」として全教科で重視されるようになりました。
この表現には次の意図が込められています。
l 主体的:興味関心を持ち、自分の学びを見通し粘り強く取り組む
l 対話的:他者との対話や協働で多様な考えに触れ、自分の思考を深める
l 深い学び:習得・活用・探究を経て概念的理解や思考力を育む
指導要領解説においては、授業改善の方向性として「アクティブラーニングの視点」が繰り返し示され、授業づくりの中心的キーワードとなっています。
次期改訂(2030年見込み)でも理念は継続され、個別最適な学びや協働的な学び、情報活用能力の育成などがさらに重視される見込みです。
現場での実感
「主体的・対話的で深い学び」を実現するために、現場ではさまざまな工夫が行われてきました。しかし、実際には「活動を入れる」「グループで話し合わせる」といった形式的な実践にとどまってしまうケースも少なくありませんでした。
また、一人一台端末の整備が進んだことで、「タブレットを使う」こと自体が目的化してしまい、本来の学びの質を高めるという視点が置き去りにされることもありました。
ただ活動させるのではなく、子どもたちの興味関心を引き出し、学びの目的や意味を実感できるような「仕掛け」を、教師がいかに用意できるかということこそが重要なポイントです。
では、子どもたちが“自分ごと”として学びに向かえるような「仕掛け」とは、どのようなものなのでしょうか。
近年、そうした問いへの一つのヒントとして注目されているのが、「教育におけるゲーム的要素」いわゆる「ゲーミフィケーション」です。
アクティブラーニングと「ゲーム的要素」の親和性
教育における“ゲーム要素”とは何か?
教育現場で注目を集めるようになった「ゲーム的要素」。これは、娯楽としてのゲームではなく、「課題の提示→試行錯誤→フィードバック→成長」といったゲーム構造に内在する“人を夢中にさせる仕掛け”を教育に生かそうとする考え方です。
例えば、
l 明確なゴール設定
l レベルアップや報酬
l 制限時間やライフ制
l フィードバックの可視化
などが挙げられます。
こうした要素は、学習者の内発的動機づけを高め、自ら進んで学びに取り組む土台を築きやすくします。
ゲーム要素がアクティブラーニングと結びつく
小学2年生の算数で、筆者が九九の授業で実践していたゲーム要素の取り入れ方を紹介します。
l 子どもが自分で覚えた段を選び、教師の前で制限時間内に九九をスムーズに言えるかに挑戦
l クリアすると、その段に対応したシールを「九九チャレンジカード」に貼れる
l チャレンジカードは教室に掲示されており、子どもたちは友達の進捗も見ること可能
l すべての段をクリアした子には、写真入りの「九九免許証」を授与
このような実践では、子どもが「次はどの段に挑戦しよう」「あの子がクリアしたから自分も頑張ろう」と、自ら学びに向かう姿勢が自然と引き出されていました。
アクティブラーニングにおける「主体的な学び」の土台として、こうしたゲーム的要素の取り入れ方は非常に有効です。
ゲーミフィケーションと教育実践の潮流
このような「学びの中にゲーム的要素を取り入れる」考え方は、“ゲーミフィケーション”と呼ばれ、国内外の教育現場で広がりつつあります。
例えば海外発のゲーム型クイズアプリ「Kahoot!」は、授業にゲーム性を取り入れるツールとして多くの学校で活用されています。これは、教師や子どもたち自身が用意したクイズ(選択式や並べ替え、記述式など)を、その場で全員が一斉に出題・回答できるものです。
筆者も、以前社会科の単元末にKahoot!を活用した実践を行いました。内容を定着させるだけでなく、「子どもたち自身がテスト問題をつくる」という活動を取り入れたのです。
単元学習の終盤、グループで問題を考え、Kahoot!に入力。クラス全体で出題し合い、誰が一番得点できるかを競い合いました。
この活動は、単なる復習にとどまらず、「どんな問いが良問か?」「どの知識を問うべきか?」といったメタ認知的な視点を育てる場にもなりました。自然と教科書を読み返し、関連資料に目を通し、工夫を凝らした出題を試みることが、地域の定着にもつながっていったのです。
実践事例と効果・課題
ゲーム的要素を取り入れた学級経営の実例
ゲーム的要素を取り入れた実践は、授業だけでなく、学級経営の場面でも取り入れられています。
学級活動として筆者が行っていたのが「夏休みビンゴ」です。
これは、夏休みに子どもたちが経験していそうな項目──「昼寝をした」「プールに行った」「そうめんを食べた」など──をビンゴのマスに書き、友達と会話しながらビンゴを目指すというもの。制限時間内にたくさんのマスを埋めようと、子どもたちは自然と笑顔で会話を交わし、教室には活気が戻ってきます。
この活動のねらいは、
l 夏休み明けの“ちょっと緊張した空気”をほぐす
l 子ども同士の交流を促し、人間関係をスムーズに再構築する
l 「新学期って楽しい!」という気持ちでスタートを切れるようにする
といったもので、学級経営におけるゲーミフィケーションの実践例といえます。
学習効果と児童の変化
こうしたゲーム的な要素を取り入れた学習では、以下のような効果が見られました。
l 自ら取り組もうとする姿勢が増えた
l 友達との関わりの中で学び合う姿勢が生まれた
l 途中で諦めない力や粘り強さが育った
特に、「学習に対して後ろ向きだった児童」が、“遊び心のある設定”によって前向きに変化していく姿は印象的でした。
課題と注意点
一方で、ゲーム的要素の活用には注意も必要です。
l 形骸化のリスク:「報酬をもらうこと」が目的化してしまい、学びの本質を見失ってしまう
l 外発的動機づけに偏る危険性:報酬(シールやごほうび)がないとやる気が出なくなってしまう
l 競争によるストレス:ランキングなどで「できない自分」を意識しすぎてしまう子も
もっとも重要なのは、ゲーム的手法は“目的”ではなく“手段”であるという視点を、教師が持ち続けることです。
表面的な“盛り上がり”のためではなく、子どもたちが「もっとやってみたい!」「自分で工夫したい!」と感じられるような、“仕掛けづくり”として活用していくことが求められます。
教育現場で今後求められる視点とは
「主体的・対話的で深い学び」を目指す上で、子どもが自ら関わりたくなるような“仕掛け”や“構造”をつくることは、極めて効果的です。
しかしそれは、ただゲーム風の要素を入れたり、グループ活動を増やしたりすればいいという話ではありません。
l この活動は、どんな力を育むためのものか
l なぜこのタイミングでこの仕掛けを取り入れるのか
l どんな状態になれば「ねらいが達成された」といえるか
といった問いを明確に持つことが、教師の役割として求められています。
タブレットやデジタル教材、ゲーミフィケーションなど、新たな教育資源が次々に登場する時代だからこそ、「何を使うか」ではなく、「なぜ・何のために使うか」を軸に授業を設計する視点が、今後ますます重要になっていくでしょう。



 地図
地図